「東大読書」〜「読む力」と「地頭力」がいっきに身につく〜
西岡 壱誠 著
こんにちは、てかてん(@tekaten)です。
今回は、「東大読書」を書評していきます。
タイトルの通り、本の読み方一つで「読む力」と「地頭力」を鍛えることができるというところに惹かれ、読んでみました。
やはり、作者が「東大生」というだけあって、
試行錯誤の末にたどり着いた「読書法」に仕上がっています。
いくつかピックアップしながら書評していきますね。
今回のトピックはこちら!
読む前の下準備で「読書の効果を最大化」する
本を買ってきたら、すぐに読み始めてしまっていませんか。
私もそうだったのですが、基本的には買ってきたらすぐに本が読みたいので、表紙を見るのもそこそこにすぐ読書を開始してしまっていました。
この東大読書では、買ってきてすぐ読むのではなく、まずは表紙や装丁、帯などから基本情報を抜き出すことから始めるそうです。
◯ この本からどんなことを学ぶのか?
◯ この本をなぜ読むのか?
◯ そもそもこの本にはどんなことが書かれているのか?
本を読む前からこの辺りを把握しておくと、読書の効果が何倍にも高まります。
「装丁読み」で読む前から情報を掴む
東大読書の中では、表紙や帯から様々な情報を抜き出して頭に入れておく読書法のことを「装丁読み」と呼んでいます。
装丁には、本の内容を端的に表現するキーワードがたくさんあります。
◯ タイトルを読んで内容をざっくり理解
◯ 表紙のキーワードから、ちょっと具体的な内容を理解
◯ 目次からさらに細かい内容を掴む
◯ 帯のコメントから、反響や読了後の効果を理解
◯ 作家の略歴や実績を知り、情報の信頼性を知る
こんな感じで、本を読み始める前から本当にたくさんの情報を掴むことができます。
確かに、出版社も「本の概要を掴んでもらう」とか「購入したくなるような言葉」を使って、装丁にはこだわり抜いていますよね。
何が書かれているのか全くわからない本を読むよりも、あらかじめどんなことが書かれていて、どんなことが学べそうなのか、そして自分はこの本から何を学びたいのかを考えておくことで、内容の理解が早まります。
読む前に「仮説」を立て、「目標」を決める
本を読む前に、仮説と目標を決めることでさらに読書の効果が高まるそうです。
先程の想定を見て、本を読み始める前にある程度の仮説を立てておきます。
東大読書で仮説を立てるならば、
東大生の読み方って特殊なんだろうな
ちょっとすると読み方は一緒だけど、頭の構造が違うのかもしれない
わざわざ本にしているのだから、どんな人でもできるよ味方になっているかもしれない。
こんなふうに、この東大読書を読む前にいろんな想像を膨らませて、仮説を立てておくのです。
この仮説を、後ほどお話しする検証読みを活用しながら、自分が立てた仮説を1つずつ確認しながら本を読んでいきます。
すると、
これは自分の立てた仮説通りだなと思うところが見つかったり、なるほどこれは仮説とは全然違ったけれどそういう意味だったんだなと理解できるところがあるわけです。
何も仮説を立てずに、本に書かれている文章をそのまま鵜呑みにするよりも、自分で考えた仮説をもとに本の文章と対話することによって、仮説が正しかろうと間違っていようと、記憶に残りやすくなります。
この仮説を立てる事と同じように、「目標を立てる」ことも大切です。
装丁読みで内容を掴んだら、この本から何を学ぶのか?という目標を決めておきます。
ただなんとなく本を読み進めるよりも、確実に目標を持っていた方が読書の効果が高まるのです。
結局のところ、「仮説」も「目標」も知識のアンテナを立てる事に他なりません。
人間の脳は不思議なもので、意識している情報にはよく気がつくようにできています。
自分に子供ができると、世間には小さな子供がたくさんいる事がわかるようになるし、子供用品がたくさんあることもわかります。
飲食店に子供用の椅子があることに気がついたり、意外と近くに子供が無料で遊べる施設があることに気がついたりします。
これは全て、「子供」というキーワードで情報のアンテナを立てたからこそ、そこに情報が引っかかるようになったのです。
「仮説」と「目標」は、その本を読む上で「アンテナを立てる」という下準備と同様なのです。
複数の本を並行して読めば、真理が掴める
やはり東大読書でも出てきました。
読書をする上では、一冊の本だけを読むのではなく「複数冊を並行して読む」ということが理想的です。
なぜかというと、
◯ 頭を切り替えてやる気を保つ
◯ 気分に合わせて読書できる
◯ 同じジャンルなら違った視点や知識が得られる
という利点があるからですね。
並行して同じジャンルの本を複数冊読むと、同じことが書かれていたり、全く違うことが書かれていたりします。
同じことが書かれていれば、それはその分野における原理原則であり、心理です。
しっかり学ぶポイントとして抑えておきます。
また、全く違うことが書かれていれば、経験則としてはどちらも正しいということになるので、
自分に合う方を選択して学んでいきます。
一冊だけでは判断できないことが多いのですが、複数冊を並行読みすることによって情報がより正しく理解できるのですね。
入門書や難解な本を組み合わせて読む
並行読みをするのなら、入門書のような簡単な本と、難解な本を組み合わせてみるとより良いです。
難解な本を読めば、いろんなことが学べますが、どうしても読み進めることができなくなる場合があります。
難しすぎて、読書のやる気も削がれますよね。
そんな時に、入門書も読んでいれば、その本が「参考書」のような役割を果たしてくれるということです。
入門書を参考書代わりに使っても良いし、入門書を先に読んで基本的なところを理解してから難しい本を読むというのもありでしょう。
いずれにしても、より効率よく内容を理解するためにも、入門書をうまく組み合わせる並行読みはおすすめです。
一冊ずつ読むなんて勿体ない
こんな感じで、一冊ずつ丁寧に読むなんてもったいないので、ぜひ読みたい本を読みたいタイミングで並行読みしてみてください。
読書好きの中には、
「一冊読み終えるまでは次の本を買わない」
という人がいます。
否定するつもりは全然ありませんが、無理にこだわりすぎる必要もないのではないでしようか。
読みたい本を読みたいタイミングで読んだ方が、読書を楽しめるし、はかどります。
前述したように、その分野の心理を掴めたり、情報の正しさを比較検討することだってできます。
試しに並行読みをやってみる、というのも面白いのではないでしょうか。
読みながらアウトプットし、読了後もアウトプットする
読書をしていく上では、「アウトプット」を意識することがとても重要です。
本を読むという行為は、「インプット」にあたりますが、知識を記憶として定着させるためにはインプットだけでは物足りません。
むしろ、積極的にアウトプットした方が記憶に残りやすいという研究結果も出ているのです。
インプットの量が必要なのは間違いありませんが、そこにアウトプットをプラスすることで、より記憶に残りやすくなります。
ポイントは、本を読みながらアウトプットをすることです。
本を読み終えてからアウトプットをすると、本の要約やまとめ、この記事のような書評を書かことができますが、やはり時間が経つと忘れてしまいます。
それなら、本を読んでいる最中に、
「おもしろいなー」
「これはためになるな」
と思ったことを、その場で発信することが良いでしょう。
ツイッターやインスタグラムを活用して、
「今読んでいる◯◯という本に、こんなことが書いてありました」
「◯◯という原理で・・・」
という感じで、本の感想を書いたり、引用を載せたり、考えたことを発信するだけでOKです。
難しく考えず、本を読みながら感じたことを発信するだけで、それが記憶に残るのですから素晴らしいですよね。
思ったことを自分の言葉で発信することで、本に書かれていたことをより自分のものとして脳が処理するようになるのです。
読みながらアウトプットすれば、理解が進み忘れにくい
さらに、読みながらアウトプットすることで、本に書かれていることに対する「理解」が進みます。
本は、常に内容を理解しながら読み進めた方が、その先に書かれていることを理解しやすくなるように作られています。
序盤に基礎的なことを書いていて、後半に応用、例題があるような本だとしたら、
序盤の基礎を理解できないまま読み進めても意味がありません。
ですから、序盤の基礎を理解するためにアウトプットしながら本を読み、後半の理解を促進します。
まさに、東大生ならではの東大読書ですね。
東大生は、日々かなり難解で大量の情報を而して記憶していますから、東大生活で得た学び方を読書に応用したような形になります。
アウトプットを意識した読書なら、「地頭力」も「読む力」も鍛えることができて、一石二鳥ですね!
読了後は要約をアウトプット
前述の通り、読みながらアウトプットすることで知識が定着しやすくなります。
「読む力」や「地頭力」を養うためにも、本を読みながら積極的にアウトプットしていきましょう。
そして本を読み終わった後は、その本の中から重要なところや伝えたいところを「要約」してアウトプットします。
ブログやSNSを活用すれば、このようなアウトプットを蓄積することができるし、自分のアウトプットの履歴としても残していけます。
多くの人に届く可能性がありますから、アウトプットで自分の「読む力」を高めつつ、影響力を身につけることにも繋がります。
本とは議論しながら読んでいく
東大読書では、おもしろい読書法が紹介されていたので、最後にお話ししておきます。
東大読書では「本と議論しながら読む」と書かれていました。
「本と議論?」と思うかもしれませんが、とても納得できた内容だったのでご紹介。
本を読むときに、
「これはこういうことなのかな?」
とか
「これはこっちの方がいいよね」
と、心の中で議論するように思考すれば、考えが深まって理解できるのだそうです。
自問自答とは少し違って、考えたことを本を読みながら確認していくような作業です。
まさに、東大流の「議論しながら本を読む」という読み方ですね。
終わりに
日本の最高学府で活躍する東大生には、勉強に関するノウハウがぎっしり詰まっています。
この東大読書は、そんな東大生が日々試行錯誤しながらブラッシュアップした読書のやり方がぎっしりです。
東大生の持つ「地頭力」や「読む力」は、努力と試行錯誤の結果で手に入れたものだとよくわかりました。
天才だから自然と勉強ができるわけではありません。
読書のみならず、あらゆることに本気の試行錯誤があったのだと。
皆さんもぜひ「東大読書」を読み、今後の読書ライフに活かしてみてください。
今日も、てかてんの書斎に遊びに来てくれてありがとうございました。
では、また。


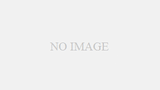
コメント